<体調改善機器認定制度>とは?

[やまもと・とみぞう]——近畿大学経営学部卒業。安価ボタンや消しゴム付き鉛筆、日本初のウェットスーツなど、独創的な商品を次々と発明しつづける山本化学工業(大阪市)の4代目社長。現在は、圧倒的な世界シェアを誇る高速水着素材やバイオラバーなどの特殊ゴム素材を開発・製造。社員1人当たり1億円以上を稼ぎ出す驚異の中小企業の社長として、多数のビジネス賞を受賞している。
山本:この制度は、家庭向け健康機器等の安全性や機能の妥当性を審査し、一定の水準に達している機器等を体調改善機器として認定することで、信頼と安心感によって消費者が自身のニーズに合う機器等の確保に資することを目的としたものです。ここでいう体調改善機器とは、人の健康・美容の増進、QOLの向上を目的とする機械器具等です。そして一般社団法人日本ホームヘルス機器協会(HAPI)が認可するというものです。医療機器と福祉用具は除きます。認定された機械器具等を「体調改善機器」と称し、認定証と認定マークが貼付されます。
菊地:<体調改善機器認定制度>が生まれる背景は、少々込み入っていることもありますので、2つに分けてご説明します。
1. 体調改善機器と機能性表示食品
菊地:日本は世界に誇る国民皆保険制度をもっています。経済的な負担感を軽くしながら、ある程度良質な医療が受けられることに重点がおかれました。結果として日本中いたるところに病院・医院がつくられ、日本人は医療へのアクセスビリティが非常に高くなりました。これは飛行機に乗らないと質の高い病院に行けないアメリカに比べて、驚異的なことでしたが、反面、これが今では足かせになってしまっている。どんなことにも光と影、陰と陽はあるものですね。
国民誰もがある程度良質な医療を安価に受けられると国が保証する———。とはいえ公的な医療サービスは「病気になって」初めて受けられる、要は医療機関に来た時から厚労省や医師会などが関わりをスタートします。病気が発現する以前の段階、つまり<健康維持><健康増進>は、厚労省にしても医師会ほか医療関係者にとって、狭い意味での「所管外」でした。
ところがこれだけ高齢化が進む現代の日本。高齢になれば誰でも、カラダになにかしらの不具合がでてくるのは生物ですから当然なことですね。でも、この不具合を感じている人の健康をそっくり国が担保するのは財政的に無理な話です。そこで、いま盛んに「セルフ・メディケア」「セルフ・メディスン」が言われるようになったわけです。
内科的なアプローチとしてのメインの処方は薬です。薬だけではなく、食事(食品)も健康にとって非常に大事であるという観点で、国は消費者庁を所管として「特定保健用食品(トクホ)」制度をつくりました。ただ、企業が同制度を利用するためには相当なバックデータをそろえなければ、申請もできないし、もちろん認定も受けられない。実際に企業サイドからは「この認定を受けるためのハードルの高さは薬事法並みだ」という声があり、認可対象もあまり増えていません。
国としても「トクホでは今後急増する高齢者の健康維持食品の指標としては間に合わない」との判断があったのでしょう。トクホの反省も踏まえ、また安倍政権の岩盤規制への風穴を開けようという空気の中、2015年4月に<機能性表示食品制度>が生まれました。この制度も消費者庁が主管ですが、いくつか画期的なことがありました。
第一に、企業側から提示するデータに「主観的なもの」が認めらました。従来は科学的・客観的なデータしか認められなかったのですが、機能性表示食品では、利用者の「これは自分には良い」という声が認められるようになったわけです。
さて、国民の健康に対する内科的処方としてトクホと機能性表示食品がありながら、なぜ外科的な処方として物理的エネルギーを使う機器の規制緩和の考えがないのか? これは行政の怠慢かのように見えます。それでも単純に怠慢だと言い切れないのは、厚労省も医師会も、医療関係者は「病気に陥ったところからが所管」ですから、未病の段階にまで嘴を挟むことには躊躇せざるを得ない。つまり、現状、健康維持・健康増進を所掌している行政は存在しない<グレーな部分>なのです。
(これは一つの例ですが、スポーツ・エクササイズジムが日本に登場した当初は、産業としてしっかりと所管する省庁はありませんでした。)
日本では「行政所管が明らかでない産業は絶対に育たない」という風土があるんです。日本の企業人は優良なジェントルマンなんですね。逆に言えば胆が小さいということになる。日本の企業人はマスコミや顧客に叩かれるのを嫌いますから、法制化されていないジャンルには手を出しません。ところが、これは海外だったらまるっきり逆で、「(法律には)何も書かれてないのだから、(何を)やってもいいだろう」と考え、行動に移す。これが世界のスタンダードな考え方なのですが、日本の企業はこの世界標準の考え方ができません。今や世界はグレーなところが主戦場になっていると言ってもいいでしょう。こうして日本人はビジネスや産業などあらゆる面でどんどん遅れています。
2. 薬事法の大改正:グレーゾーンと自己責任
菊地:2014年11月に、これまで薬事法と呼ばれていた法律が「薬機法」(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)と改称され施行されました。 法改正のポイントは多岐にわたりますが、再生医療品等を管理対象に含んだことは画期的なことでした。
先端医療である再生医療には、まだまだ未知・未確認の事柄がたくさんあります。それを従来の薬事法と同様な方法で規制していては、医療者ばかりでなく、医薬品・医療機器メーカーも再生医療に積極的に取り組むにはハードルが高くなりすぎてしまい、日進月歩の先端医療に我が国が出遅れてしまいかねませんからね。
また医療行為を受ける側に対しても、治癒率の情報を開示されたうえで治療を受ける自己責任の考え方を制度化していくことも、保守的すぎて革新技術が生まれにくい日本の医療界が革(あらた)まるきっかけになるでしょう。
ところで「薬事法大改正」では、健康管理ソフトを単体で医療機器として承認するようになりました。
これまでも医療に関するソフトウェアは、厚労省がCTやMRIなど各々の機器に関するソフトを各々の機器とセットで認可していました。
一方、ここ数年激増しているスマホやウェアラブルの健康管理アプリは、従来の薬事法では対象にはならないグレーというよりはむしろダークな状態でした。しかし、これらソフトが発するバイタルサインを完全に無視できるものではなくなってきた以上、ある程度信頼を置ける機関・団体による審査の下で認証することが必要になってきました。ここで誤解していただきたくないのは、これは新たな技術や商品に対する規制強化的なものではないことです。続々と増える健康管理ソフトを、どこの省庁も所管しないという無責任な放置状態にしないとともに、各企業に「自らのソフトの弱点を把握・明確化してもらう」「その弱点に対する対応を用意させる」の2点、つまりリスクマネジメントをそれぞれの企業に求めるようにしたわけです。しかも、新たな商品と技術の許認可の代行を専門性と実績のある民間の既存業界団体に委託する、「民活」なのです。
厚労省からの研究依頼を受けた私共も検討を重ねて厚労省が音頭をとって、JEITA(電子情報産業協会)、JAHIS(保健医療福祉情報システム工業会)、JIRA(日本画像医療システム工業会)といった団体に声をかけ、健康管理ソフト単体に対して審査・認証ができる団体として、2014年8月にGHS (ヘルスソフトウェア推進協議会)が設立されました。これまで所掌が明確でなかった、ダークゾーンを民活によって解決することができるようになったことは、日本の医療厚生行政史に残るエポックなことと考えています。
我々がやらずに誰がやる?!
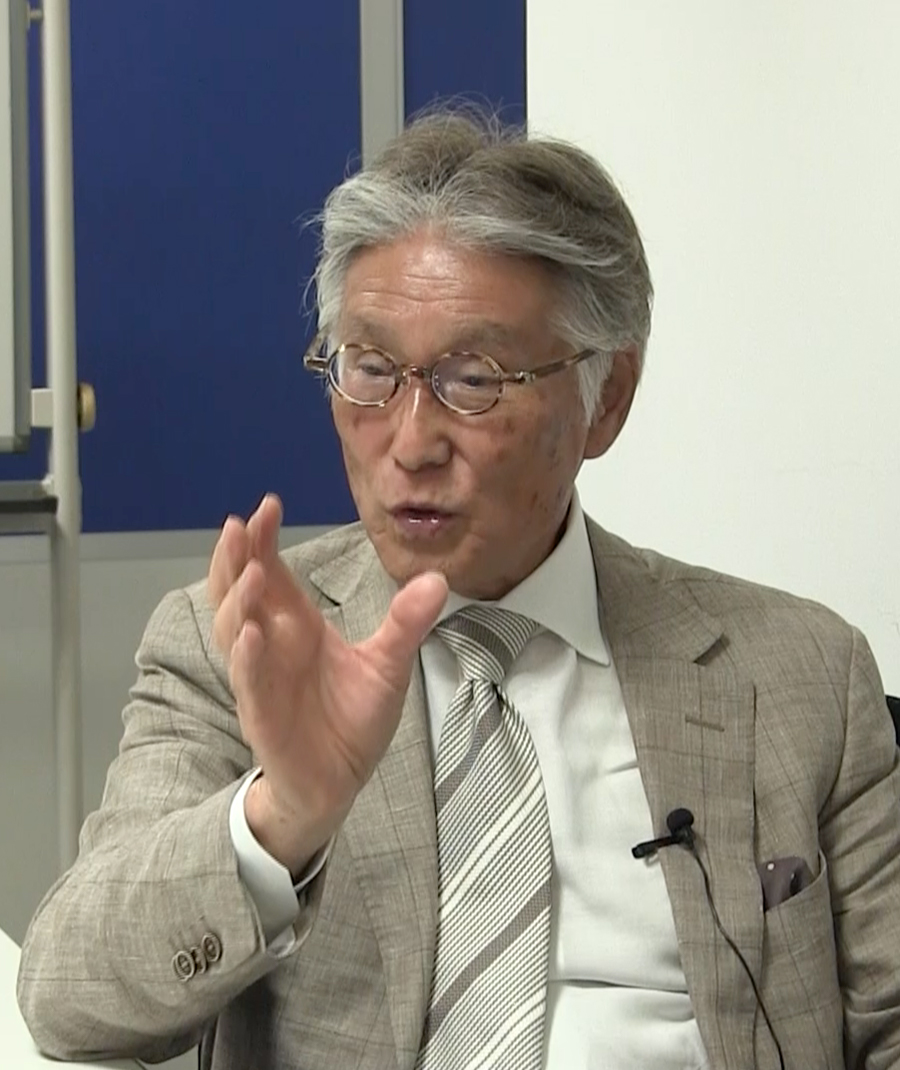
[きくち・まこと]——慶應義塾大学大学院工学研究科修了。工学博士。医用工学研究の第一人者として、防衛医科大学校教授・防衛医学研究センター長・副校長を歴任。現在、公益財団法人医療機器センター理事長、国立研究開発法人日本医療研究開発機構プログラムディレクター、一般財団法人在宅ケアもの・こと・思い研究所理事長、ふくしま医療機器開発支援センター理事長など、多数の要職を務めている。
菊地:題材が変わりますが、血圧計はいうまでもなく医療機器です。人命に深く関わる、デリケートな医療機器ですが、認定の基準はJIS(日本工業規格)で、しかも第三者認定でOKなんです。さらに定義として「まずカフを巻き……」とあるため、「非接触」な血圧計は今のところの認定は難しい状態のまま———。こうした古い規格では審査できないグレーの問題が露呈してきています。
古い規格に縛られて、新しい技術を活かせないままでは、技術革新ができないことはもとより、市場の掘り起こしと拡大もできません。現状はグレーな扱いを受けている技術や製品には、大きな可能性が秘められているかもしれないのに、です。
グレーゾーンのままだった部分に対して、中立かつ公的な立場からキチンと評価・審査して認定することができるようになってこそ、日本の社会全体へ大きなインパクトを与えうるのではないか?
長年、医工連携の立場で「産官学臨(臨床)」の現場に携わり、いわば業界団体内部にいる立場から、こうした機会を求めきていたわけですが、「医療未満」の一般の方々にとってはご自分の健康のこととして切望されています。さらに国の医療財政、ひいては日本の産業経済にも貢献できうる……。ところが、あいかわらず健康機器はグレーな「無所管状態」。これを行政が自ら動いて変えることはなかなか厄介なのです。 また全く関連性のない業界・団体が関わって方向性を変えることもできないでしょう。
ここまで考えた私は、3年前のHAPIの理事会で「世の中の変化を先導するのは団体としての責務ではないでしょうか?」と当時の稲田会長に申し上げました。私自身、理事でもあるので「我々がやらなかったら誰がやるんですか!」と言ったことを覚えています。
HAPIは「医機連(日本医療機器産業連合会)」に属し、40年以上の歴史をもつ品格ある団体です。稲田会長は私の声を聞いてくださり、年次総会で、稲田会長自らのご判断で、新しい健康機器の認証制度をHAPI自身が立ち上げるため、異例の若さで山本会長が抜擢されました。
山本:そのとおりです。菊地先生からのご提案に対し、HAPIとしても積極的に取り組もうということになったのですが、関係省庁の鉄壁を突き破るため、討ち死に覚悟の<ヒットマン>(笑)として私が会長に選出されました。
菊地:体調改善機器というものを各省庁や団体に認めてもらう条件については、永年医療工学連携に関わってきた私の経験上、厚労省はもちろん、産業面だったら経産省、人材的な面では文科省、あるいはAMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)といった組織のどこにどなたがいるかということを把握していましたので、彼らの「スカートの裾を踏まない(各省庁の規制に触れない)」ための言質として、次の3つを上げました。
まずは、<体調改善機器は非医療機器なので効果効能をうたえない>ということを大前提としたうえで、
第1は「安全性」。これは医療機器もまったく同じです。それを使うことで使用者に危害を及ばないこと。
第2が「品質保証性」
第3が「自己責任で購入者が判断できる情報公開性」
以上の3点です。
体調改善機器ように従来のジャンルでは捉えにくい、法律的な裏付けのないグレーゾーンのものを制度化するためには、山本さんのようなフレキシブルな方でないと、説得力のある発言はできないでしょう。それを見抜かれたからこそ、前稲田会長も、創設以来異例の若さで会長に抜擢されたわけですね。
山本:我々が製造販売している家庭用医療機器は、世間では「医療機器であって医療機器でない」そんな中途半端な認識を持たれていました。ですが、今回の菊地先生からいただいたご提案は「中途半端な認識の部分を拡げてもらおう」というのではなく、これからの健康管理機器のために「HAPIだからできることを、HAPI 自身でやろう」という積極的なものでした。ですから私自身も前向きな気持ちで臨み続けることはできました。とはいえ厚労省や経産省との折衝は、やり始めた当初はキツかったです。なんといっても医療機器について各省庁の担当者と折衝に来るのは、私らと比べて格段の大メーカーさんばかりです。
それでも、完全に民間の協会で立ち上げるということと、HAPIならではの有利な点を何度も確認繰り返し、審査のための「ガイドライン」、「制度の定義」、「制度の名称」といったことがらを一つ一つHAPI内部で確認し、それを省庁担当者に上げ、修正指示を受け、HAPIで確認の繰り返しでしたが、3年がかりでやっと体調改善機器認定制度ができました。
先ほど菊地先生があげられた重要な条件を、繰り返しになりますが補足させていただきます。
まずは大前提として、体調改善機器は「非医療機器」であり、「薬事法としては雑貨(雑品)」なんです。ですから「効果効能」をうたう(表示する)ことはできません。「不当表示」は改めて言うまでもなく、絶対にしてはならいことですからね。
第1に重要な「安全性」とは、「使用者へ危害を与えない」ことです。体内に入れるサプリメントのような「内科的」なものについては専門ではないので詳しくないのですが、いったん口から入れてしまったら取り出すことができませんから、それゆえの品質・表示の厳正さが求められているでしょう。いっぽう体調改善機器、たとえば「外科的」な器具は、使用を止めれば、ほぼただちに危害が発生しにくくなる。そのためにはタイマーなどで使用時間を制限する必要がありますね。
第2の「品質保証性」。現在の日本では、健康機器には法的規制が無いのを良いことに、出所も品質も不明な、あらゆるジャンルのものが市場に出回っています。そして主に国外メーカーと販売業者ですが、「消費者からの問い合わせ先が不明」なのがごく普通な状態になっています。日本国内の工業製品ならば当たり前のことが、外国製品ではしばしば行われていないのです。その結果、日本の健康機器や業界全体がマイナスイメージを被りかねません。こうした状況に歯止めをかける意味でも、製造品番号も把握する「品質保証性」を厳守します。
第3「自己責任で購入者が判断できる情報公開性」ですが、これは購入者自身が自己責任でお買い求めいただくものであるということです。購入をお考えの方が判断していただきやすい、わかりやすい説明表示を必ず行うこと。特に評価審査内容についてはもちろん、審査がどんな方たちによって、どんな経緯で行われているかということも、全てHAPIのHPで確かめることができます。
以上の条件を備え、審査をクリアした商品には認定証が交付され、認定マークを貼付することができるようになります。
第2の「品質保証性」については、HAPI会員企業の大半が医療機器販売業であり、しかもISO13485に則ったQMSを構築していたことも体調改善機器認定制度を設定する大きなバックグラウンドになりました。
(※ISO13485:医療機器向けの品質マネジメントシステムの構築、運用のための国際規格)
(※QMS:Quality Management System品質管理システム)
菊地:3つの条件を詰めていく段階で各企業の営業担当の方々からお聞きして初めてわかったのですが、こうした条件は大手量販店に営業をかける際に仕入れ担当者から、必ず言われ続けてきたことだそうです。実社会では当然のことだったんですね。
山本:HAPIが設立されて以来(前身:全国家庭用健康治療機器工業会)、40数年の間の新製品誕生の推移は決して多くありませんでした。医療機器は新製品を開発するにも認可を受けるためにも、非常に多くの資産投入が必要なので中小企業単体ではどうしても限界があるうえ、販売対象が自ずから絞られてしまいます。ですからHAPI自身を家庭用医療機器に縛り付けておくこと自体が、各企業の事業ばかりでなく、業界全体に閉塞状況を招いていました。この状態に稲田前会長は強い危機感を抱いておられ、そこに菊地先生からの<体調改善機器>というご提案をいただいたわけです。「健康維持」「健康増進」というキーワードでしたら、高齢化が進む市場ですから、非常にポテンシャルが高い。しかも、医療機器に限らず衣食住あらゆる業界から参入することが可能になったわけです。
山本:まず第1回目の審査ですが、認定制度の発足時点で、HP上に申請のための必要事項はすべて公開していました。けれども医療機器の申請に不慣れな企業さんでは申請企業の書類的不備という事案がいくつか起こりました。第2回目は前回の経験を踏まえて、実際の審査委員会の事前に、企業担当者と面談の場が設けられ、申請に対する予備的なサジェスチョンが行なわれるようになり、審査はよりスムーズに行われました。
ただ、委員以外の同席は一切認められない審査には、改めてたいへん厳粛・厳正な制度であると、思わず襟を正しました。こうした「中立」「厳正」「公開」な審査を積み重ねることで、「<体調改善機器認定>されているのなら安心だね」と消費者の信頼を得ることができることと、同様に企業側に伝われば新たな参入・挑戦を促すことになるのでしょう。
実際にファッション業界とのコンビネーションによって、まもなく新製品が生まれようとしています。
自己犠牲の醸成と今後への期待
山本:地味な作業の積み重ねではありますが、体調改善機器認定制度をより多くの、建築やファッション、家電、自動車……今までまったくご縁がなかった異業種の方々にも広く認識していただき、これを活用したビジネスを生み出し、その継続によってエビデンスを積み重ね、さらなる新しいステップに挑戦する———こうした流れが生まれることを強く願っています。
実はこの制度ができるまで、HAPIの会員全体が顔を合わす機会自体は、年次総会と賀詞交歓会しかありませんでしたが、今後、まず年1度は東西の会員企業とともに、新規入会を考えておられる企業にもオブザーバーとして参加いただくことにしました。こうして、新しい出会いが異業種同士をジョイントし、今までにないコンビネーションから全く新しい商品・ビジネスが生まれてゆくだろうことを、期待しています。
菊地:ところで、現状、日本人はあらゆる法に守られすぎています。医療に関していえば、国民皆保険制度が完備された結果、国が100%の医療を与えてくれることに甘えて、自己判断と自己責任を考える習慣がなくなってしまいました。医療に関して何か事あれば企業や国が訴えられかねない状態は、新しい技術やサービスを生み出すうえで大きな障害になっています。
山本:私どもの製品もアメリカのFDA(アメリカ食品医薬品局)の認可を受けているものがありますが、あれは「一定基準を満たしているからFDAは認可するけれど、使用についての保証は自己責任だ」というものです。
菊地:アメリカは特に自己責任が強く求められますね。でも、それが世界標準なのであって、日本人は国に甘えすぎてしまっています。
「物事をなあなあで済ます」自己責任感の無さは、「島国の農耕民族だから」という説と同根かどうかはわかりませんが、日本の学者は知見が狭くて自分の専門にしか関心がありませんね。
これは医学研究者のケースですが、国際医用生体工学連盟(IFMBE)の会長を長年務めてきた関係上、国内外の学者さんとたくさん面談してきました。新たに学会に来られたプロフェッサーに「20世紀の医学に最大に貢献したメディカル・ディバイスは何ですか?」と尋ねると、日本の学者たちは、外科医なら「ロボティック・サージェリー(ロボット支援手術)」、眼科なら「OCT(眼科三次元画像解析)」といった感じで、ご自分の専門で役立った個別の医療機器名称をあげてこられます。でも、外国人のプロッフェッサーたちは、決してこんなことを口にしません。彼らからは「メディカル・ディバイスはニューコンセプトを医学に与えてくれた」あるいは「医学の教科書を書き換えてくれた」というような答えが返ってきます。
ニューコンセプトとはどういうことかというと、たとえば、かつて外科医の「能力」は、お腹から背中まで大きく切り開くような大手術が出来るか否かにかかっていました。ところが腹腔鏡手術が常識となった現在は、そうした技術はほぼ無用になったいっぽう、機械制御やデータの読み方など、異なる次元の技術の修得や知識の研鑽が求められるようになっています。かつての医学の教科書は全く書き換えられる時代になっているのです。
ところが、日本の研究者はご自分の狭い専門のことしか考えていません。
南アフリカのような国の大学でも修士論文の審査には、必ず最低1名の外国人が入るんですよ。
こうした日本人特有の「閉じた感覚」は医療界だけではなく、ビジネスの世界でも言えるのではないでしょうか。日本のベンチャービジネスのプロモーションで、自社開発したテクノロジーの良さを語ることにばかり時間を費やし、そのテクノロジーを使ったビジネスモデルで事業や市場をいかに変えることができるか? というコンセプトに割く時間はごくわずかしかないことも、よくある話です。
世界の医療機器メーカートップ20のなかに日本企業は2~3社、しかも17~18位という下位にしかランクインしていません。なぜか? これは医療機器以外の業界でも当てはまることですが、日本では売上げ何百億円クラスの企業規模でも、金融やメディアは、みんな笑顔で穏やかに接してくれます。そんな環境ですから取り立ててイノベーションをする必要もなければ、しようとも思わないでいられる。
ところが何千億円クラスの企業となると、収益を上げ続けるためには常に世界中のライバルとガチンコ勝負をしていなければならない。このクラスの企業ではイノベーションは生き残るためには必要条件なのです。幸か不幸か、日本国内の医療機器メーカーのほとんどが、恒常的なイノベーションが求められる状態ではないので、画期的な技術開発が生まれにくいということはあります。
また医療機器産業は多品種少量生産の典型で、医機連(日本医療機器産業連合会)に加盟しているだけでHAPIも含めて21もの団体があるんです。ということは、どこも決して大企業ではないので、各社ごとでのイノベーションは難しいという事情もありますね。
それから医療(機器)界で人材面の問題点は、ベーシックな学力が圧倒的に不足しています。一般教養としての科学全般はもちろんですが、生理学や薬理学、栄養学などは、その方面に進まないかぎり教育を受けることもない。先ほど、日本のプロフェッサーの医学の捉え方で外国の医学プロフェッサーに大きく水をあけられている話をしましたが、この差は大学以前に受けている義務教育の幅の差から来ていることは間違いありません。
若いベンチャー起業家から、よく「型破りなイノベーションをやるぞ!」的な発言が聞かれます。しかし、はっきり言っておきましょう。「型破り」というのは、過去の全ての型を知り、自らの経験として理解したうえで初めてできること。思いつきや口先だけで「守破離」はできません。
山本:はからずも先生の口から「守破離」をお聞きできるとは。実は高校時代から少林寺拳法をやっていまして、全部で618(?):要山本氏再確認ある「技」のうち、自分は五百いくつかまで身に着けたものです、だいぶ忘れてしまいましたが(笑)。少林寺拳法でも「守破離」についての教えがあります。まず全部の型を学び練習を繰り返して自家薬籠中の物にする。これが「守」で、これまでの積み重ねを「破」るからこその「型破り」なんですね。そして「離」で自分なりの独立した技を紡ぎ出してゆく。
ですから、「御社のようなゴムのウエットスーツを作るメーカーが、なぜX線遮蔽エプロンなんて型破りなことを」とよく言われますが、本業の技術を知り尽くしたうえでの展開ですから、僭越なようですが、ごく自然な流れなんです。
まだ始まったばかりの制度ですが、<体調改善機器認定制度>の社会的認知度を高めてゆくことで、かつては思いも寄らなかった業界・業種の企業と、技術と信頼を堅実に培ってきたHAPIの既存企業とが、さまざまなコラボレーションを組むことで、本当の意味でのイノベーションを起こしてゆきたいですね。
菊地:今日はグレーやダークゾーンという言葉をあえて使ってきましたが、要は「いま光が当たっていない<よく見えない>ところ」ですね。でも光線があたっていなくとも、そこには何かある。赤外線は可視光線ではないので、<よく見えない>どころではないのですが、それを認識することができたおかげで、熱源やセンサーといった有用性を引き出すことが可能になりました。
医療という特殊な色眼鏡をかけたまま人間社会と技術文明を見ていると、体調改善機器というポジションは無きが如しですが、その眼鏡を外しさえすれば、その有用な存在は際立ってきます。これからの体調改善機器が、私たちの既成概念に縛られずに、幅広い進化形を見せてくれることを願ってやみません。



