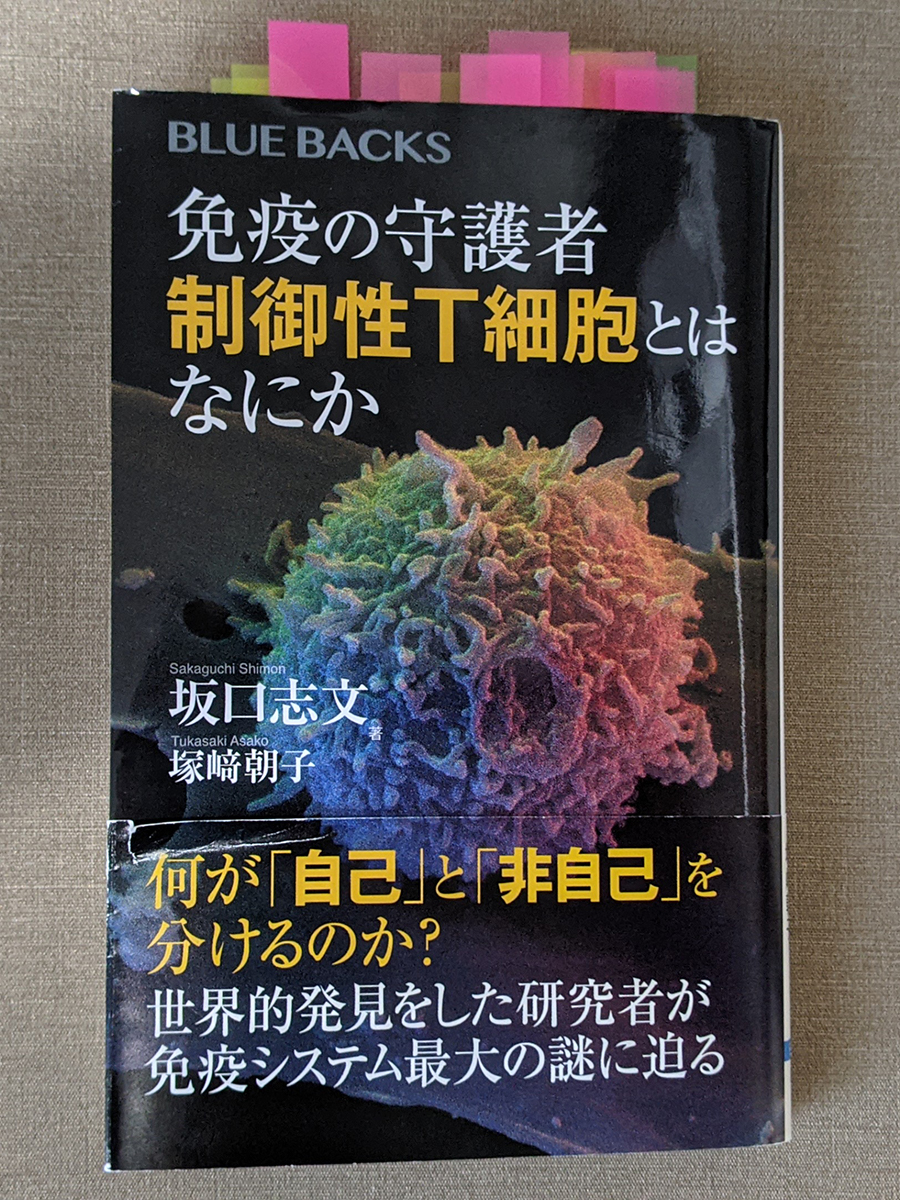日本先進医療臨床研究会代表 小林 平大央
ガンと自己免疫疾患の両方に正反対の働きで関わる制御性T細胞

現・大阪大学特任教授の坂口志文先生が1995年に発見した「制御性T細胞」(通称「Tレグ」)という免疫細胞をご存じでしょうか? Tレグは通常の免疫細胞とは違って外敵や異物を攻撃する細胞ではなく、免疫細胞が敵を攻撃するのを止める働きをします。近年、Tレグが自己免疫疾患からアレルギー疾患、炎症性疾患、そしてガンにまで深く関わっていることが分かってきました。
自己免疫疾患とは、免疫が自分の細胞や組織を攻撃してしまう病気で、先進国では人口の約5%程度が発症しているといわれています。例えば、関節リウマチや多発性硬化症、1型糖尿病、炎症性腸疾患などです。
自己免疫疾患の患者は、血液中のTレグ濃度が低いことが分かっています。Tレグ濃度は通常、血液中のヘルパーT細胞の5~10%程度存在しますが、自己免疫疾患の患者では5%を下回る方が多いのです。自己免疫疾患の患者の血液中のTレグを測り、値が低い場合はTレグを増やす治療を行うことで症状が改善・治癒する可能性が高いと考えられています。
一方、ガン患者は血液中のTレグ濃度が高いことが知られています。ガン細胞は自分自身を守るために腫瘍のそばにTレグをたくさん集め、キラーT細胞などの攻撃を止める盾として利用していると考えられています。そのため、ガン患者の場合は血液中のTレグを減らす治療を行うことで、併用するガン治療の効果が高まるのではないかと考えられています。
免疫とは、〝自己〟と〝非自己〟を区別し、生体に害をなす非自己(細菌やウイルスなど)から自分の細胞や臓器を守るためのシステムです。しかし、なぜ免疫細胞の攻撃を止める必要があるのでしょうか? その理由は、生物が自分一人では生きられないからだと考えられています。
人体にとって有用なビタミンや脂肪酸などの各種の栄養成分を作ったり、必須栄養素の吸収を助けてくれたりする腸内細菌や、人体を外敵から守るバリアとなる皮膚常在菌など、人間は多くの有用な細菌と共存して暮らしています。もし、これらの有用な細菌を異物として免疫細胞が殺してしまうと、必要な栄養が得られない、外敵から身を守れないなど、たいへんな不都合が生じてしまいます。そのため、免疫細胞には攻撃する対象と攻撃しない対象を分けるしくみがあり、自分の細胞や自分にとって有益な異物は攻撃しないようになっているのです。
特定の抗原(ターゲット)に対して攻撃しないしくみを「免疫寛容」と呼びます。特に、自己の細胞に対する免疫寛容を「免疫自己寛容」といいます。ところが、免疫寛容は、時として排除すべき非自己に対しても起こってしまうことがあります。例えば、C型肝炎に感染した方が妊娠して胎児がC型肝炎ウイルスに感染すると、新生児が誕生して成長した後でもC型肝炎ウイルスに対する免疫が発動されず、抗体も作られないということが起こります。
こうした免疫寛容がなぜ起こるのかを解明したのは、オーストラリアのウイルス学者フランク・マクファーレン・バーネットと、イギリスの生物学者ピーター・メダワーです。バーネットは免疫寛容が起こるしくみについて次の仮説を提唱しました。
「免疫には自然免疫と獲得免疫があり、獲得免疫の主力の1つであるB細胞は侵入するさまざまな抗原に対する抗体を持つ無数のクローンを作ることができる。クローンは無限ともいえるほど多種類が作られるが、中には自己成分や有用な共存成分に反応してしまうクローンも作られてしまう。ところが、自己成分や共存成分に強く反応するクローンは、免疫系が未成熟な時期(胎生期から出生後2日程度まで)に周囲の自己成分や共存成分と接触することで排除されて存在しなくなる。これが免疫寛容のしくみである」
バーネットの仮説を実験によって証明したのがメダワーです。メダワーは、マウスの実験で胎生期に別のマウスの細胞を入れると、細胞を移入されたマウスは誕生後、細胞を提供されたマウスの臓器を移植しても拒絶反応を起こさないことを確認。バーネットの仮説を証明し、技術的な介入によって免疫寛容を後天的に起こす可能性を見いだしたのです。バーネットとメダワーは「後天的免疫寛容の発見」によって1960年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。
自己細胞を攻撃するT細胞も、T細胞の攻撃を止めるTレグも「胸腺」という組織で教育されます。胸腺では、未熟なT細胞が免疫寛容の教育を受け、合格したT細胞だけが「ヘルパーT細胞」「キラーT細胞」「Tレグ」などに成長して血液中に出されます。残念ながら、落第するT細胞もいます。自己成分に過剰に反応するT細胞はアポトーシス(自殺)してしまいます。逆に、排除すべき非自己成分にまで反応しないT細胞は成長できず自然消滅してしまいます。このように、胸腺で成長して血液中に出てきたT細胞とTレグのバランスによって、免疫の暴走は抑えられているのです。
ところが、胸腺でのT細胞の教育のしくみがありながら、約5%もの人は自己免疫疾患を発症してしまいます。その背景には、胸腺でのTレグ教育の要となる遺伝子「FoxP3遺伝子」の存在があります。FoxP3遺伝子が発現していないTレグは、免疫の暴走を止められないことが判明しているのです。そのため、自己免疫疾患の患者では、エピジェネティクス(DNAの塩基配列を変えることなく、環境などの後天的な要因が遺伝子の働きを決めるしくみ)によって、FoxP3遺伝子の発現に不具合や欠損などが起こっているのではないかと考えられています。
FoxP3遺伝子を発現させるスイッチは、両親や先祖から引き継がれた生活習慣などの後天的なエピゲノム(エピジェネティクス情報の集まり)によります。そのため、生活習慣の改善やある種の治療などによってエピゲノムを変更し、FoxP3遺伝子の発現スイッチをオンにすることが可能であると考えられています。免疫の暴走と制御のしくみに関する最新の知見を背景に、自己免疫疾患やアレルギー疾患、炎症性疾患、ガンなどに対して人間を対象とした臨床研究が世界中で行われはじめているのです。
日本先進医療臨床研究会ホームページ