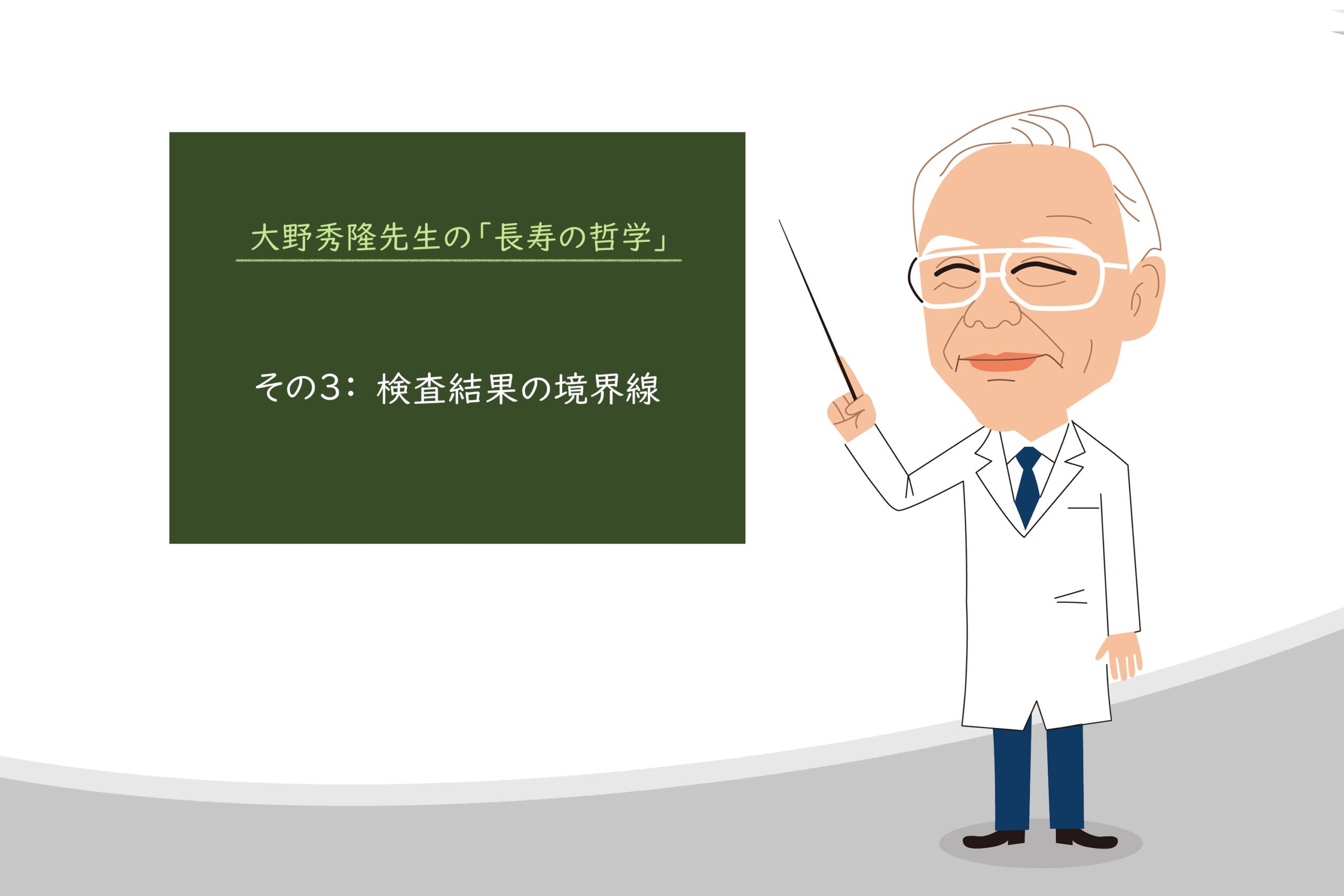理学博士 大野 秀隆

ある会社の社長さんが、「毎月、診察を受けに病院に行っているけど、通院するだけで半日かかってしまう」とぼやいていました。
順番を待ち、ようやく呼ばれた後の医師とのやり取りは、あっけないもの。カルテを見ながら「何か変わったことはありませんか?」「特に変わったことはありません」「では、同じ薬を出しますので来月にまた来てください」と、2~3分で終了してしまうそうです。その社長さんは、もう少し診てほしいなあと、いつも思っているとのことでした。それだったら、自動診察機を用意して、「ベツニカワリハアリマセン」という声と一緒に薬の処方せんが出てくるようにしたらいいと思うのですが。
一方で、やりすぎる検査は患者にとって必然性がなく、ときに大きなデメリットを伴います。全身がだるくて不快な頭痛とめまいを覚えた人が、ある病院を訪れました。内科・眼科・耳鼻咽喉科・脳外科と渡り歩き、1ヵ月間で約200もの項目に及ぶ検査を受けたそうです。
その間、納得のいく説明は一度もなく、その人は安心感を得られずに治癒を諦めたそうです。病気の診断がつかないまま、次から次へと受けさせられた検査の負担によって症状が悪化する例は少なくありません。
検査そのものの技術的なエラーや副作用の後遺症に悩む人もいます。期待する医療を求められないばかりか、検査に振り回されることによる心の痛みや傷は、体の悩み以上に深刻になることがあります。
いまの医療は、検査に頼りすぎる傾向があると感じます。症状から想定される何種類かの病気を診断するための情報を求めて、多くの検査が行われます。その結果、さほどの成果(異常所見)を得られないと、想定する病気の範囲を拡大し、関連した検査を増やしていくのです。人間ドックでもその傾向があります。「検査をしておけば何かがわかるだろう」という発想です。「病気を見落としたくない」という、医師としての不安感も働くのかもしれません。
私たちの体調は常に心に支配されています。体そのものには病気がなくても、ちょっとした心のゆがみがきっかけで体調が崩れます。それが発展すると、やがて本当の病気になってしまうことも多いのです。いずれにしても、どこからが病気で、どこまでは病気といえないのか——その境目は、まさに正常と異常の仕分けといえるでしょう。
体調の悪い原因を、すべて検査でつかめるはずはありません。自覚症状がどんなに病感の強いものでも、検査にさほどの異常が現れないこともあります。たとえ検査結果に多少の異常があっても、果たしてそれが自覚症状と因果関係を持つものかどうか…その答えは「なんともいえない」場合が多いのです。さほどこじれた体調でなくても、健康上の不安を持つ人が多い時代です。その不安を解決する機会として健康診断や人間ドック、さらに各種の検診がありますが、いずれも役立つものでなければ、時間とお金の無駄遣いになりかねません。
検査結果の正常・異常とは何を意味するのでしょうか。本来なら、一本の線や一枚の壁で明確に仕切ることができないものを、無理に区分するのが検査です。その境界をちょっとずらせば異常がたちまち正常となり、正常が異常となります。検査には、正常値・基準値・標準値・生理値・健常値・理想値など、さまざまな表現がありますが、大勢の人を2つのグループに仕切るという考え方です。これらの数値の境界線は、さも絶対的な意味がありそうで、実は幻のようなものです。
私たちの心身には個性があり、クセもあります。全身の状態は日々変化し、検査結果も変動します。その変動の波の様相は、同じ検査を繰り返して受けないと分かりません。従って、検査の正常値は、あくまでも目安として見たいものです。肝心なことは、数値の結果が正常であれ異常であれ、実生活を自分らしく過ごせるかどうかです。